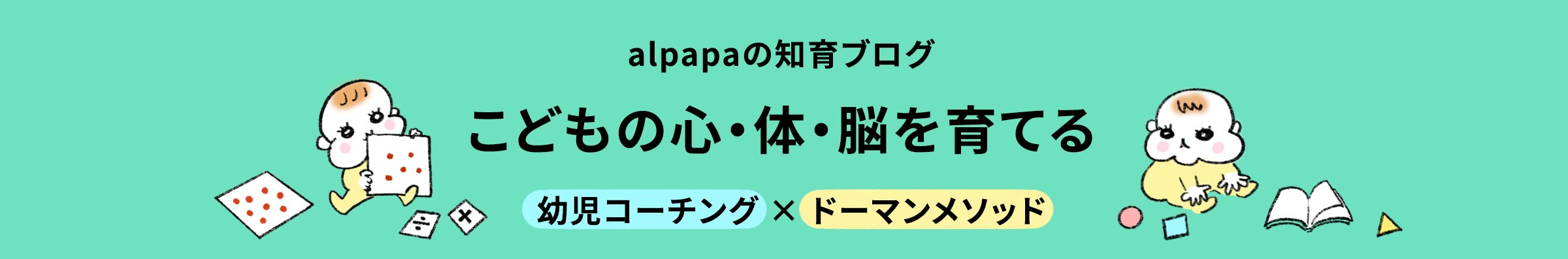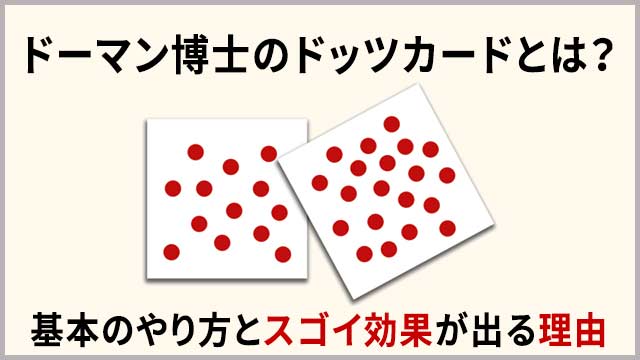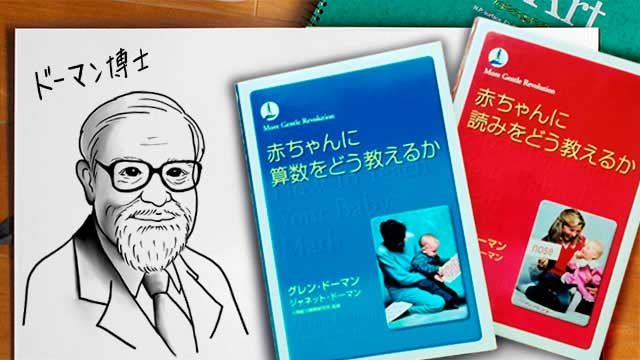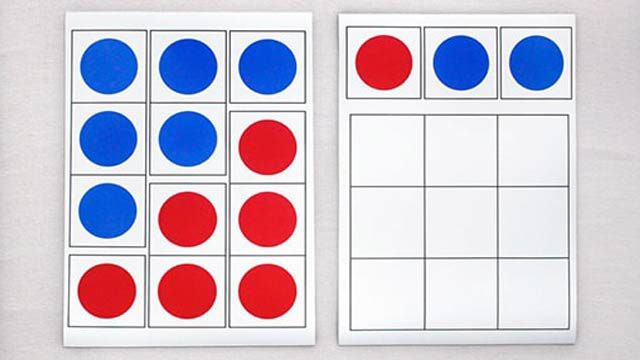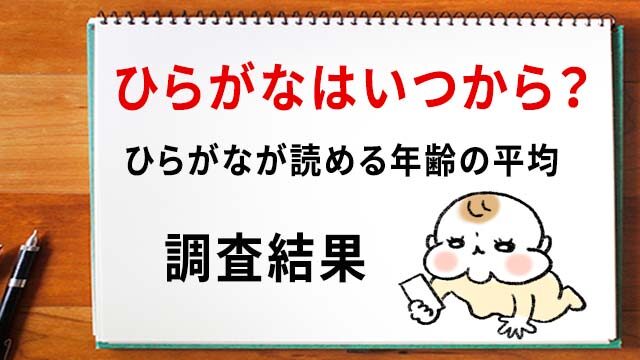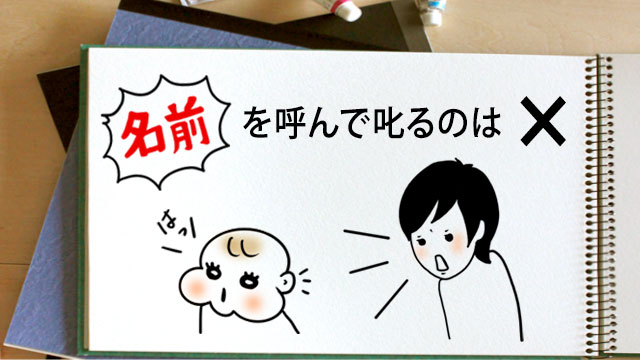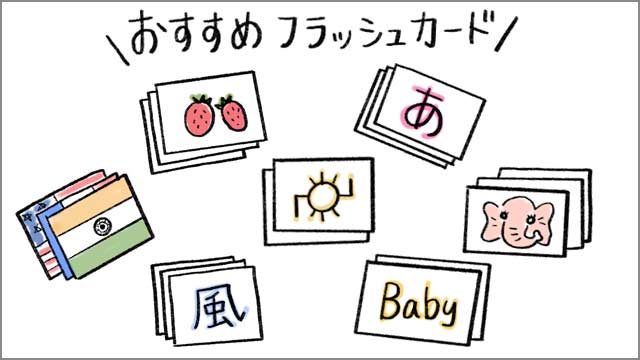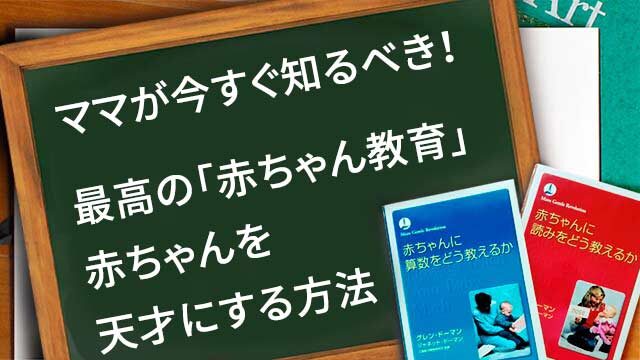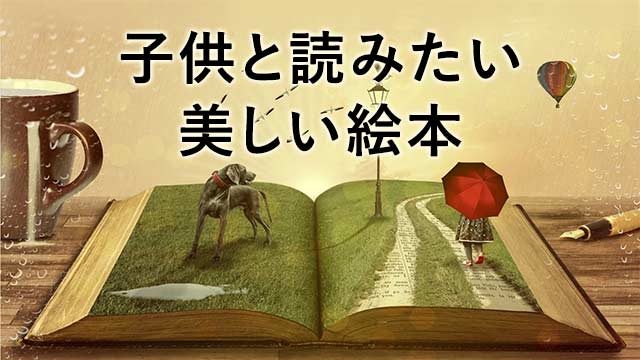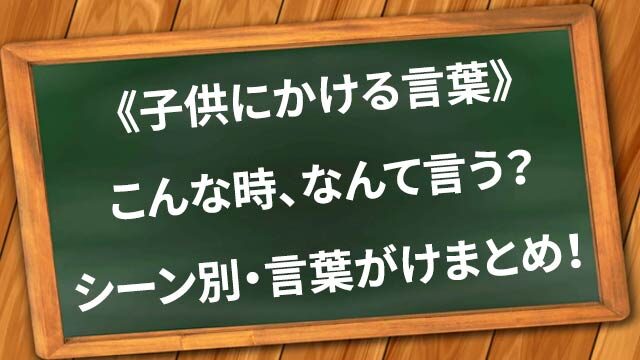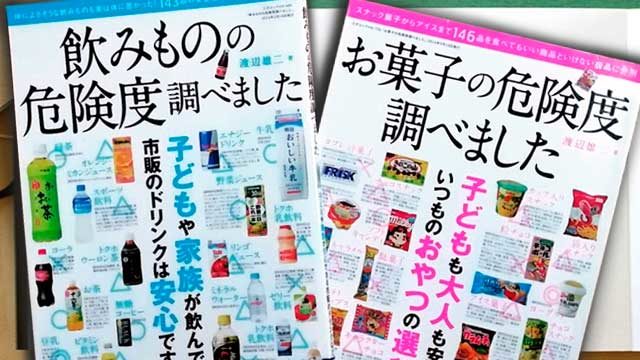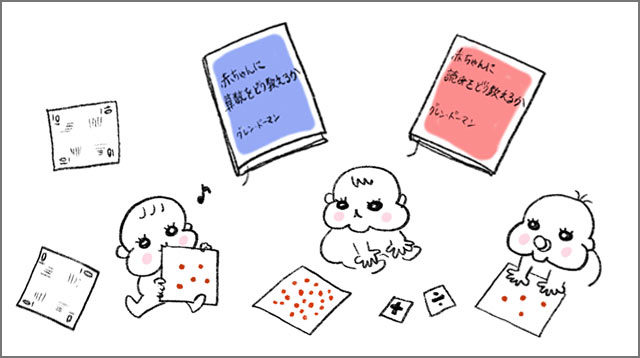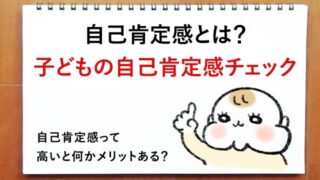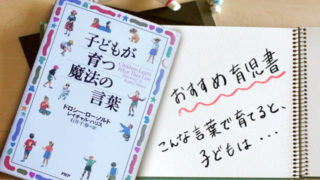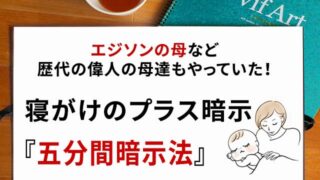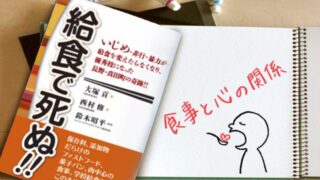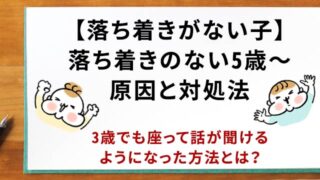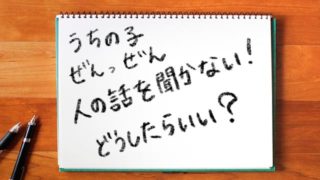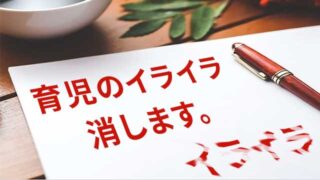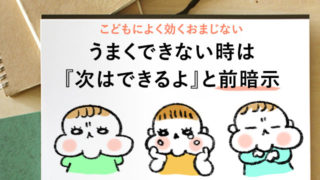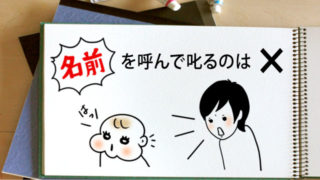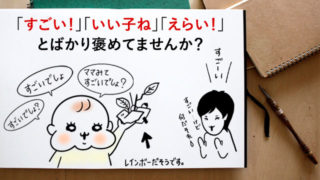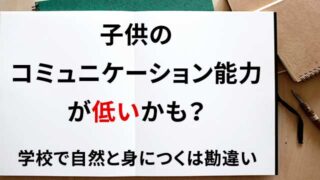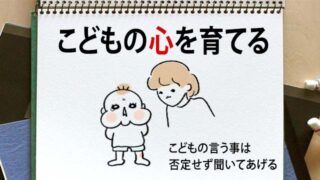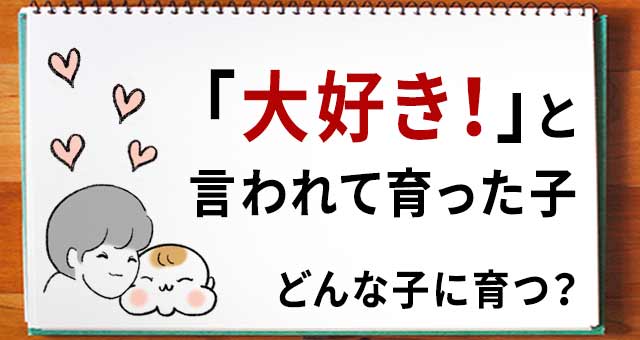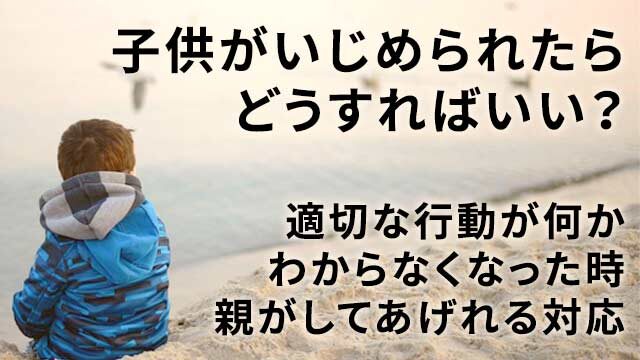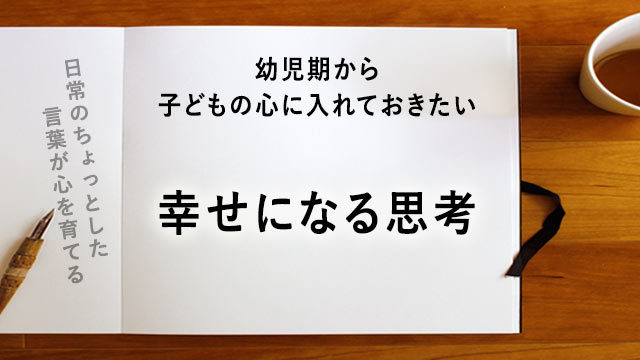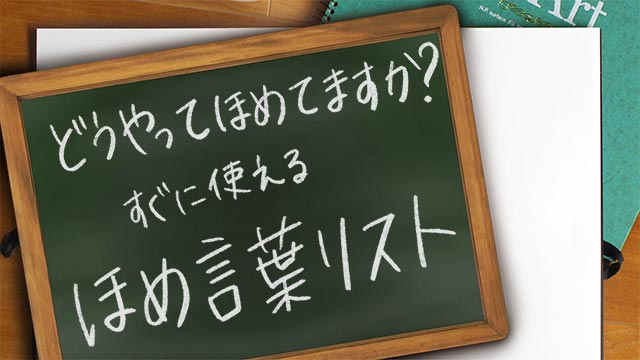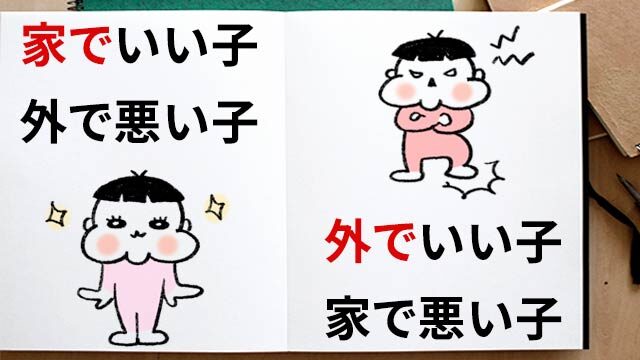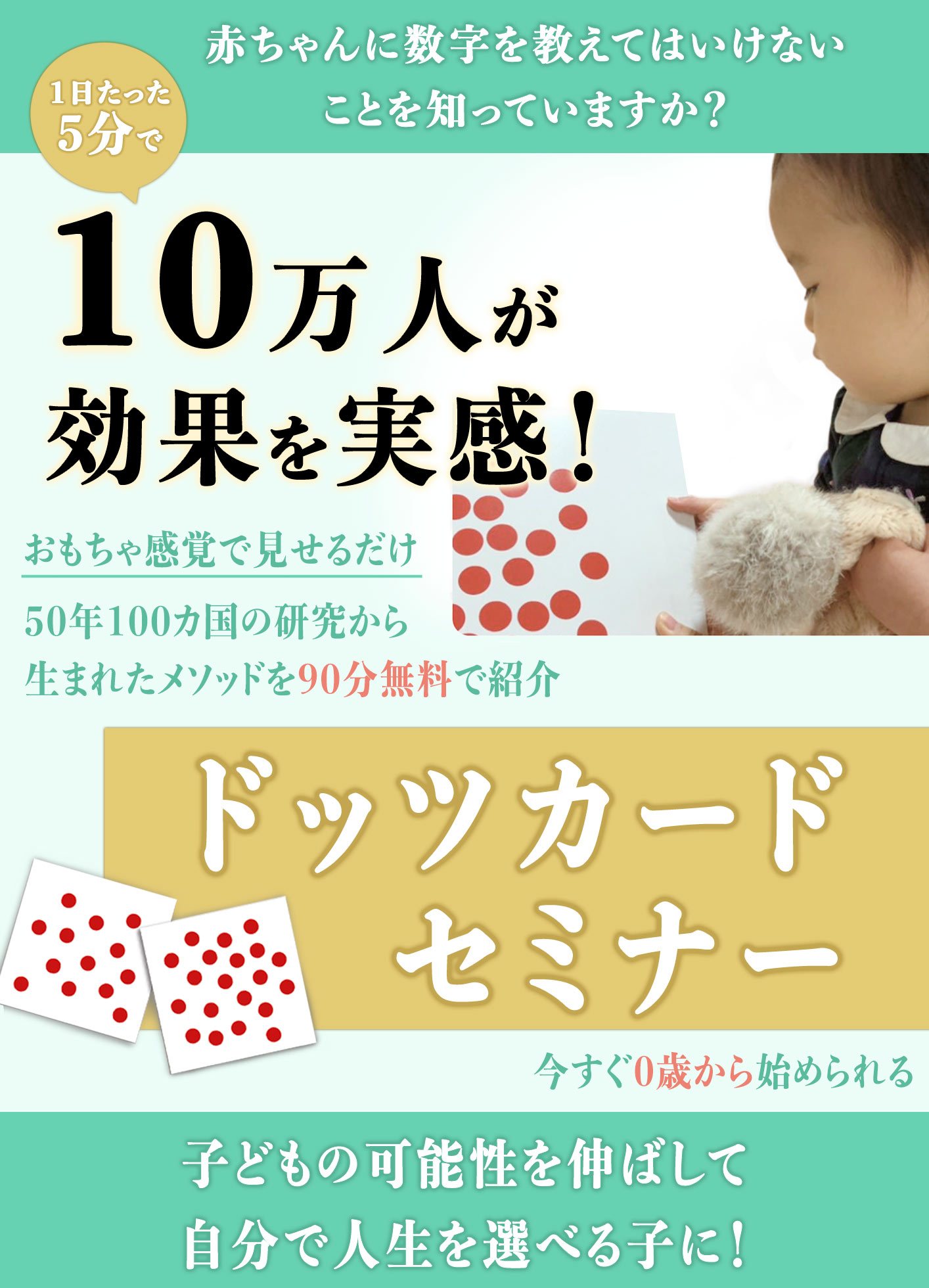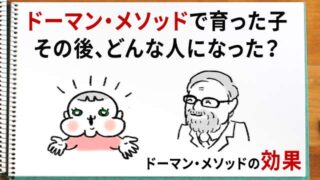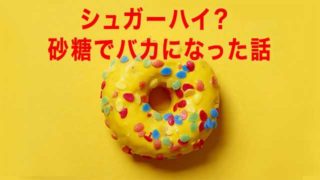こんにちは、alpapa(@alpapa)です。
0〜6歳の子供の性格の原因は、
はやり親の影響が大きいです。
しかし、親の性格=子供の性格ではなく、
親の対応の結果が、子供の性格に出てくると言われています。
この記事では、
子供の性格に影響するのは
親のどんなところか?
与える環境や友人関係は?
親がどう対応していけるか紹介していきます。
目次
子供の性格が悪い原因は親です、が・・・。
「子供の悪いところは親のせい」
よく聞くフレーズですが、
その通りです。
というのはちょっと極端ですね…。
子供の性格は、
遺伝による元々の気質、家庭環境、など総合的な要素の結果なので親だけが原因かというとNOですし、
でも、遺伝子から与えられた環境まで、
結局は親が原因といってしまえばYESです…。
人の性格は、
生まれ持った気質x環境から作られます。
生まれ持った気質に良いも悪いもなく、
それをどう活かすか?次第です。
生まれつきの気質に対して、
親がどう対応してあげたか、
どんな環境を与えてあげたか、は人の内面に大きく影響します。
一般的には、
遺伝(生まれつきの気質):環境(6歳以下ならほぼ親)の影響は
0歳で⇒100:0
5〜6歳で⇒50:50
その後、反転し
6歳〜大人で⇒30:70
になります。
(遺伝x環境で相互作用します)
つまりどんな気質の子が生まれても、
6歳になる頃には
その子の半分は親によって作られています。
その後、環境の影響が次第に大きくなるので、6歳以降の子供の性格に影響を与えるのは友達(人間関係)と言えます。
『朱に交われば赤くなる』
というやつですね。
なにはともあれ、
0〜6歳は心の土台を築く重要な時期です。
幼稚園選びや生活環境、遊ばせる友達、与えるものなど、何をするにも親が選択することだらけで、親の影響下にあることは否定できないところですね。
人格と心は、幼い頃に100%親から作られて、ほぼ一生変わらないと言われています。
引用元「頭のいい子にする最高の育て方」/はせがわわか(著)
ただし!
親の性格=こどもの性格
親の子供への対応=その結果、こどもの性格に反映
です。
なので親がどれだけ大切に育てても、愛情がうまく伝わってなかったり、自己肯定感を下げる叱り方をしていたりと、子供が不満を抱えつづけていれば、それは性格にも反映してきます。
特に性格形成に重要な3歳まで、まだまだ影響を強く受ける6歳までは、子供が何を感じて毎日を過ごしているかに気を配ってあげてください。
(心理学的にも、人は生まれてから6歳までに人生の脚本を書き、一生をその脚本通りに生きる。と言われています。⇒詳しくはこちら)
0〜6歳の幼児は、
性格が悪く見えても、
基本的にそこに悪気はありません。
幼児は基本的に
・やりたい事はやってしまう
・好きな事しかやりたくない
・相手のことは(まだよく)考えれない
・愛情クレクレ星人
↑
これが普通だと思って見てあげてください。
これに加え、0〜6歳のうちは
イヤイヤ期・幼児反抗期(3歳)・4歳の壁などの時期は、一見「性格が悪い」と受け取られがちですが、これは
脳の発育段階で起こる成長イベントで、同じく本人に悪気はありません。
子供は、
見て聞いて知っていることから真似していきます。
ですので、親や周りの大人が子どもに見せる事&聞かせる事=真似しなさいと教える事です。
子供の言動で気になる事があれば、
日常で子供が何を見聞きしているか見直してみてください。
子供の性格は、
親や周囲の大人の見せる言動、
そして自分へ対する反応や接し方によって変わっていきます。
それら自分に起こったことを、
『子供がどう感じてきたか』で心が作られていきます。
たっぷり愛情を与えているつもりでも、
本人が愛されていると感じてなければ、愛情不足を経験します。
子供のためを思って言ったことも、
本人が「否定された」と受け取れば、心にモヤモヤが溜まっていきます。
では、具体的に親のどんな対応が原因で、
どうなりやすいかを紹介していきます。
子供の性格が悪くなる原因
そもそも性格が悪いって何?
という方は記事後半へどうぞ。
それでは、
対応の改善ポイントを紹介しますので、
思い当たるふしがある方はご参考ください。
また、
優しい子に育てるヒントは⇒こちら
言葉がトゲトゲしていて生意気な子の対処法は⇒こちら
子供の性格に影響する『自己肯定感』を下げる対応

子どもには持って生まれた気質があり、
それぞれに得意・不得意があります。
まずは、
どんな性格でも受け入れてあげてください。
「そんな事すると嫌われるよ」
「悪い子はママ嫌い」
と自分が否定されていては、
他人に優しくするのは難しいです。
「みんなは仲良くできるのに!」
「できないと将来困る」と短所を改善したくなりますが、いきなり「悪い所を直しなさい!」というのは、小さい子供にとってかなりのストレスです。
そして0〜6歳の幼児期は、
短所の改善に適した時期ではありません。
できない事があっても、
とりあえず、はじめからできなくて大丈夫です。
それより、
まずは長所を伸ばすことに重点をおいてください。
長所をたっぷり伸ばし、
身についた自信が、
できない事を克服するやる気なります。(できる子に変わる長所伸展法はこちら)
逆に、自信もやる気もない状態で、
「他の子はできるのに!」と人と比べたり、短所の改善を強いると、ますます自信をなくし、自己肯定感が下がり性格にも悪影響です。
子供の自己肯定感チェックテストはこちら▼
自己肯定感とは?子どもの自己肯定感をチェックする簡単なテスト
子供の性格が悪くなる原因『親の言葉』

子供は「バカ」と叱ればバカになり、
「どうして意地悪するのよ!」と責めるほど意地悪な性格にまっしぐらです。
間違っても
「ほんっと性格悪いわね!」
「あなたケチね、わがままだし」
なんて言葉をかけないようにしてください。
親が言うほどその通りの性格になります。
『親が子供にかける言葉』は、
想像以上に深く性格に影響します。
性格だけでなく、能力、学力、そして運にまで影響します。
いつから影響するかというと妊娠中からですが、とにかく6歳ごろまでは言葉に気をつけて育ててください。
子供の脳は、まだ完成していません。
脳波も意識構造も大人とは違います。
この状態はどんな状態か、わかりやすく言うと洗脳状態です。
6歳までの脳は、
言葉の暗示にかかりやすく、親のいうことをなんでも信じ、冗談は通じません。
6歳までは、今まさに
「どんな脳になるのかプログラミング中」で、親や周囲の言葉を集めてプログラムしている最中です。
0~6歳を育てるママに知ってほしい事↓
ママは絶対知るべき!6歳までの子供の心、間違えた子育てをやり直したい
「育児と言葉」に関するオススメの本も紹介しておきます↓
子供の育て方で迷ったら読む本【子どもが育つ魔法の言葉】の感想
子供の性格が悪くなる原因『親が与える人間関係』

例えばもし、
周囲に否定的な言葉を使う大人がいれば、子供はその影響を受けます。
お行儀の悪いお友達がいれば、まねしておふざけしたり、悪い言葉遣いを覚えます。
人は真似をして学んでいくので、
周りのすべてが学びの対象です。
これは共感能力や社交性あると見て、
良い面もあるのですが、困るほどであれば誘われても遊ぶ必要ありません。
幼児のうちは、
お友達や環境は親が選んであげれます。
大人の集まりに、
子供を連れて行く時も気をつけてください。
仲がよくても愚痴を言う友人、子供に悪影響な話をする人がいるなら連れて行かないのが無難です。
日常と違うイベントは刺激が強いので、
幼児の記憶に刷り込まれやすいです。
もし、いじわるな冗談を言われて傷ついたりしたら、「5分間暗示法」などで傷を流してあげるのも効果的です。
引くほど効いた5分間暗示法のやり方↓
エジソンの母もやっていた!【五分間暗示法】寝がけのプラス暗示
子供の性格が悪くなる原因『親が与える食生活』

見落としがちですが、
食生活はメンタルにも学力にも影響します。
コンビニ食や食品添加物、ジャンクフード、お菓子やジュース、これらの乱れた食生活から、精神まで乱れて不安定になっている子もいます。
最近、買い食いばかりさせていて、
落ち着きのなさやキレやすさ、問題点が目立つという場合は、一度、食生活の改善を心がけてください
コンビニ弁当、添加物で育った子▼
【食事と心の関係】コンビニ弁当、カップ麺で育った子供はこんな子でした
落ち着きがない、
集中できない、
大人の話をきけない、
そんな子達が「食」を変えただけで変わった事例▼
【5歳〜】落ち着きがない子、じっと座っていられない子供の原因は?
子供の性格が悪くなる原因『親のきまぐれ』

親が気分屋だと、
こどもは混乱してわがままになります。
例えば、いつもはダメといっていることを、親が気分次第で「今日はいいよ」と許したり、逆にいつもはいいよと言うことを「今はダメ!」と親の気まぐれでルールを変えると、子供は『何がいいのか悪いのか』わからず混乱します。
また、感情的に叱った後で、
「さっきは悪かったな…」と親の罪滅ぼしのために、お菓子を与え甘やかすと、子供は「悪い事して怒られたのに、ご褒美がもらえた」と混乱します。
親や大人の気まぐれな態度によって、
基準がわからなくなるため、さじ加減をはかる『ものさし』がしっかり育ちません。
さじ加減を考えずものを言うので、
周囲からみたらわがままな子に映ります。
しつけのルールはコロコロ変えず、
一貫した態度をとってください。
例外が起きる時は「今日は誕生日だから特別ね」「おばあちゃんが来てくれた時だけね」など、きちんとルール外になる理由を説明しましょう。
うちの子、人の話を聞かない!3歳で聞けない原因と6歳までに直すコツ
子供の性格が悪くなる原因『子供を叩いてしつける』
子供を叩いてしまうことによる悪影響は、山ほど報告されています、その報告をまとめると、叩いてしつけると脳がダメージを受け性格が歪むです。
そもそも叩いて恐怖や痛みで従わせて、いい影響が出るわけないです。
子供を叩くことの悪影響についてはこちらをご覧ください↓
【子供を叩く親】子供を叩いてしまう影響、叩くのをやめたい時の克服法
どうしても育児でイライラして暴言を吐いてしまう方、イライラが止まらない場合はこちらをご覧ください▼
育児でイライラする時やってみて!育児カウンセリング不要の解消法
育て方間違えた?そもそも性格が悪いって何?

ここまで話してなんですが…
そもそも『性格が悪い』って何?
⇒それは、
ただの相手の受け取り方です。
わがままでも「子供らしくてかわいい」と言う人もいれば「性格わるい!」と言う人もいるので、正直、あまり他人の評価に振り回されすぎないようにする事も大切です。
学校などで態度を注意されたからといって
家庭で『まったく、恥ずかしい子ね!なんでそんな事も出来ないのよ!』と親まで敵になってしまっては、子供は居場所がなくなります。
こういう時は、
一方的に否定したり叱りつけず、
まずは気持ちを受け止めてあげてください。
それから、叱らず善悪を伝えます。
決して「悪い子ね!」など人格否定した言い方はせず、悪い行為の方を正してください。
一度や二度伝えるだけでは、
すぐにできるようにはなりません、
粘り強く何度も伝えていってください。
また、
ポジティブな性格が良い、
ネガティブな性格は悪い、と思われがちですが、そうとは限りません。
ネガティブだからこそ慎重に行動して成功した、という事もあるので、活かし方次第です。
そして
幼児によくあるお友達とのトラブルは
一見悪い事のように見えますが、実は学びが多く、成長するチャンスです。
親が一方的に解決しようと思わず、
問題解決の仕方を少しづつ学ばせてあげてください。
子供の自制心が育ってくるのは、
4歳ごろと言われています。
4歳は「予測脳」が発達し、順番、どうぞ、ゆずりあい等、ルールや約束をしっかり守ったり、少しづつ状況を予測して行動できるようになります。
この時期にじっくり、
コミュニケーションの大切さを教えていってあげてください。
「仲良くできるよ」と前暗示かけるのも効果的です。
子供がお友達と仲良く遊べない・うまくできない時は『前暗示』
また、自制心が育つ4歳あたりは、天使の4歳と呼ばれる反面『4歳の壁』とも呼ばれます。
4歳の壁にぶちあたっていると
一見、性格がわるい!親のしつけがなってない!ように見えますが、そうではなく脳の発育段階で起こる「心が成長する時期」なだけです▼
まるで子供の性格が悪く見える!『4歳の壁』

ママを悩ます『4歳の壁』って何?
2歳のイヤイヤ期はよく知られていて、
親も周りも「こういう時期なんだなぁ」と寛大です。
2歳児がどれだけ「いやぁぁ!」とのたうちまわってても「性格悪い!」と言う大人はいないでしょう。
ところが….
お話も上手になって、
自分の意見も言える、
食事・トイレ・着替えなど基本的なことが自分できる、理由を言えば理解できる4歳ごろになると、急に▼
・いままでできていた事(あいさつ、どうぞ、食事etc)、できるはずのことを「しない」「甘える」
・自分の思い通りにいかないと、怒って友達に乱暴な事を言ったり、ふてくされた態度をとる。
という事が起こる子が、
実はけっこういます。
これは、脳が発達し、
・いろいろな事が理解できる、
・幼稚園のルールもわかる、
・大人の言う事もわかる、
・「僕はこれがしたい」という自分の気持ちもわかる
・「今日はこうしよう、これができる」と予想もできる。
例えば、4歳の年中さんは
・いじわるはダメと知ってる。
・幼稚園にはルールがある事もしっている。
「でも、あのおもちゃは僕一人で使いたかったんだ!」
「今日は絶対、Aちゃんと一緒にブランコしたかったの、Bちゃんとは嫌なの!」
↑
そしてこれをすると、
先生やママに怒られることも、なんとなく予測できる….。
これらの急激な心の成長に本人が戸惑って不安になり、壁にぶち当たるという成長イベントが『4歳の壁』です。
しかし、社会性を守りつつ、自我を通す術はまだないため、イライラして乱暴な事を言ったり、不安になって甘え、できる事をしなかったりする時期があります。
これを見るとママは、
「なぜ?!私の育て方が悪かったの..」と不安になるかもしれませんが、
こういう時は、
『この子の心が成長している時期なんだなぁ』と受け入れながら、地道に肯定的な言葉がけを続けていってください。(ママはけっこうしんどいですよね…)
4歳は社会性も少し身につき、
理解力も高くなってくる頃ですが、
まだ『相手の気持ちを理解する・感情や行動を抑制する』までは脳(前頭前野)が発育していないのです。
『感情をコントロールする・判断する・相手の気持ちを汲み取る』という、人を人らしくする脳の部分⇒前頭前野は発達がゆっくりで、急速に発達するのは8歳頃からと言われています。
それまでは『人の気持ちを考えなさい!』というのは脳的に難しい事です。
しかし、だからと言って放置していいというわけではなく、幼児でもまったく考えれないわけでもないので、マナーやルール、コミュニケーション能力の基礎をコツコツ教えていく事が大切です。
子供の性格に影響する『叱り方・褒め方・感情の出し方』
子供の気になる一面がある場合、
日常での叱り方、褒め方、を少し工夫してみてください。
どんな言葉で叱っているか、
褒めているか、子供の気質に合わせて変えていくことも効果的です。
気をつけたい、叱る時の言葉についてはこちら↓
【子供のダメな叱り方】親として最低限ここだけは押さえておきたい事
褒める時は、
子供の心を満たしてあげるのが◎
褒める時の対応についてはこちら↓
子供の褒め方『すごい!えらい!』は良くないの?伸ばす褒め方のコツ
もし子供が、
感情を溜め込んでモヤモヤとしている場合、このようなセラピーで感情を吐き出すことも効果的です↓
【子供向けパステルアートセラピー】パステルアートの描き方と心の掃除
親の地道な対応と
言葉がけの積み重ねがジワジワ心に効いてきます。
子供の性格が悪くても【絶対に】してはいけないこと
それは、
子供を否定することです。
「そんなことする子は嫌い」
「イジワルなあなたはダメ」
「いい子じゃなきゃダメ」
こんな風に『そんなあなたはダメ』と自分を否定されては、どんどんひねくれていきます。
子供は、
たとえ意地悪でワガママで悪い子でも、
ママに受け入れてほしいと思っています。
『どんなあなたでも大好きよ』
と、言ってほしいと思っています。
子供だけでなくママも、本当は心の底で
「そんなあなたでもいいよ」「よくない所があってもいいじゃん」と受け入れられたいはず。
我が子のどんな一面も、
否定しないであげてください。
悪い事させ放題でOKという事ではなく、悪い行動は注意しますが、あなたは悪い子!と本人を否定するのはNGということです。
それに「性格が悪い」
というのは、あくまで受け取り方次第。
ワガママくらい全く気にしないママも、
子供らしくて可愛いというママもいます。
ワガママに見えても子供が、
自分の感情をしっかり表せたり、
意思表示ができる事は良い事ですし、それもその子の個性です。
しかし、
わがまま放題では集団生活で苦労します。
どうすればいいか?
こんな時、子供の個性をつぶさず、
集団でもうまくやっていけるようになるコツは『コミュニケーション能力』を鍛えることです▼
コミュニケーション能力の低い子供、原因は?コミュ力は自然に伸びない
ママが子供の話を否定せず聞くコツ▼
子供の心を育てるコツ『子供の言う事は、否定せず受け止める』
3歳で気になる性格は6歳ごろまでに対応を

なぜ6歳までかというと、
6歳になり小学校へ入ると子供の世界は「友達」になります。
個人差はありますが、
6歳以降、子供はだんだん自分の世界に親を入れていくれなくなります。
親が寄り添っても、次第に影響力は薄れていきます。
小学生ごろになると、
ママのいうことは無視しても友達の一言で一喜一憂したりします。
例えば、
親がどれだけ「かわいい」と褒めても、
友達が「ダサい」と言った服は着なくなります。
親がどれだけ
「テストの点なんて気にしなくていいよ」と言っても、友達に「えっ赤点だったの!?」と笑われたら泣いて帰ってきます。
そしてもう一つの理由は、
脳は6歳までに9割完成します。
6歳を過ぎたら手遅れというわけではありませんが、性格、思考ベースなど頭の土台が9割出来上がってからは、変化につながるまで時間がかかります。
万人に当てはまる育児の「正解」というのはありません。
しかしもし、子供に気になる一面がある場合「この子にはどう接してあげるのがいいか?」と、6歳前に一度見直す機会を作ってみる事をおすすめします。
0-6歳は手をやく時期ですが、
親の声がしっかり潜在意識に届いている時期でもあります。
この間に、
将来への幸せの種をたくさん巻いてあげてください。