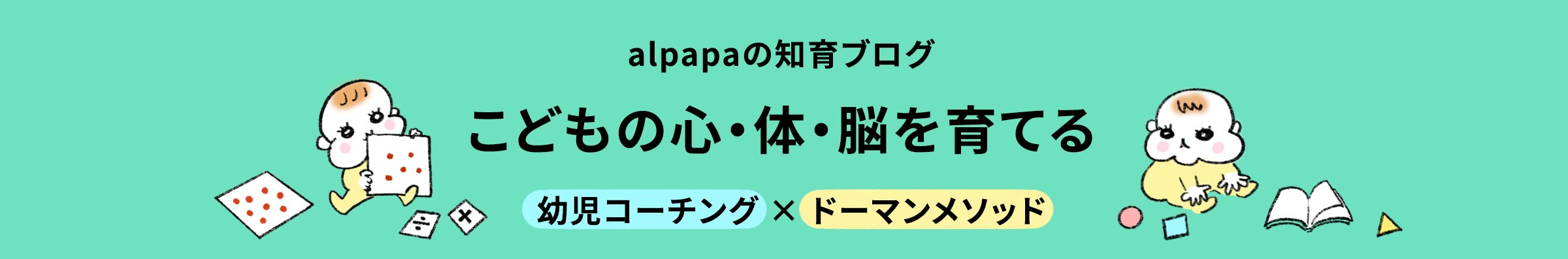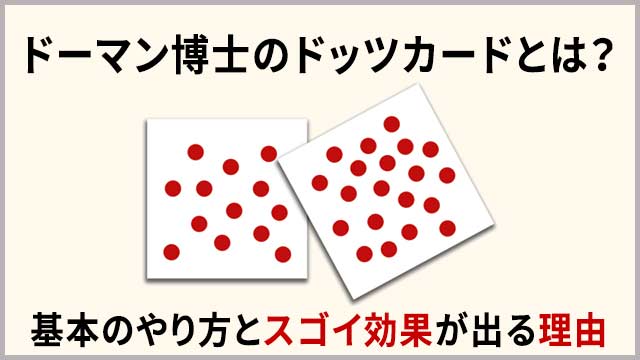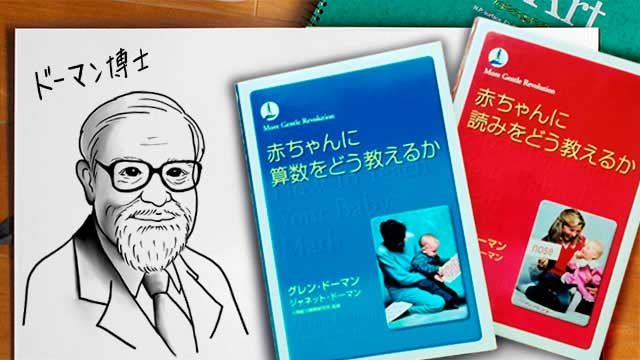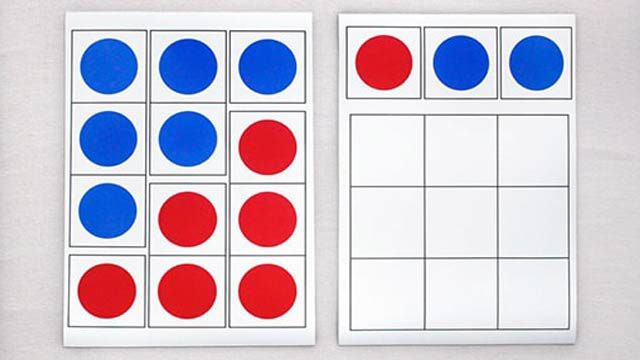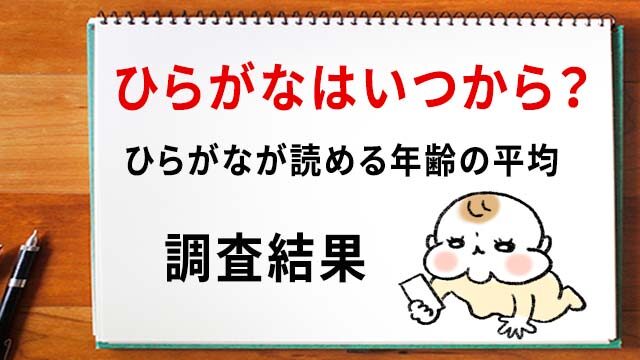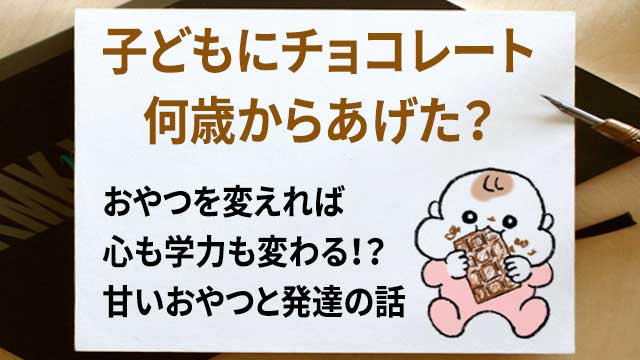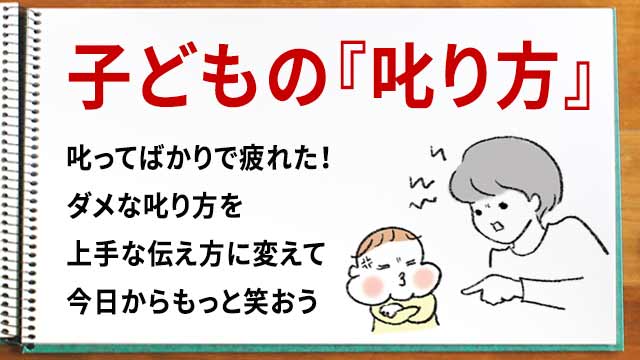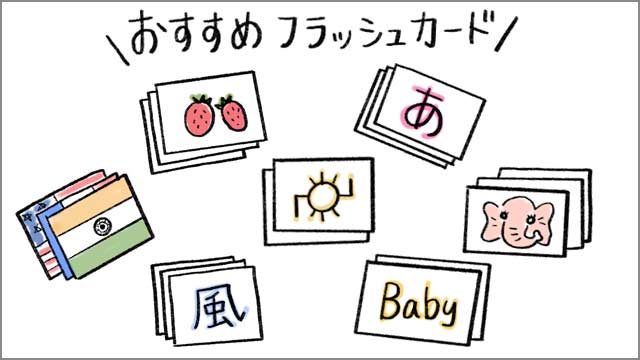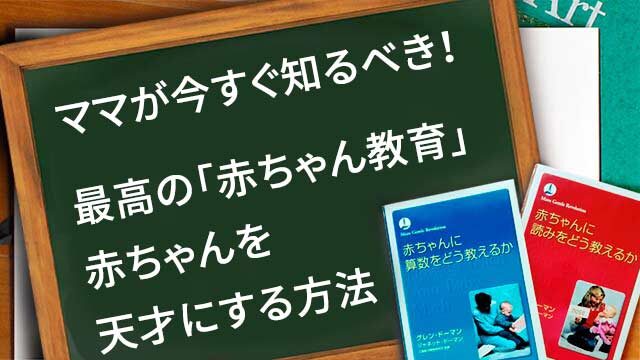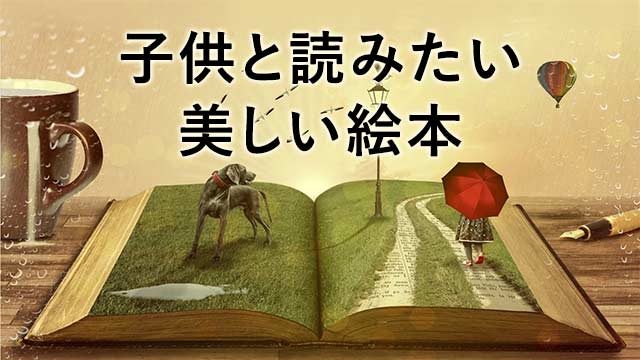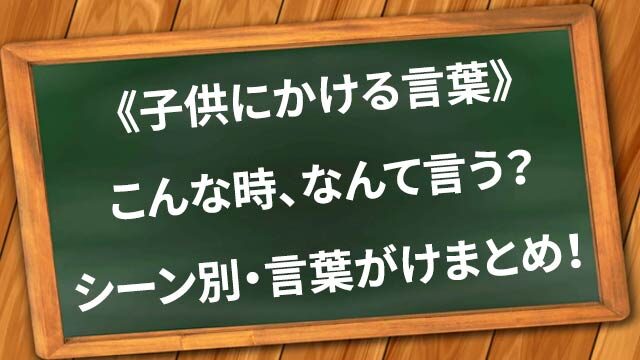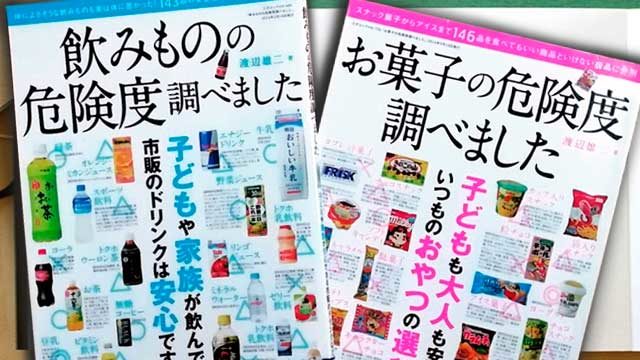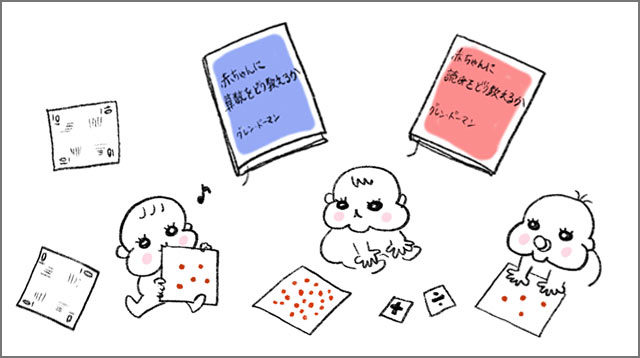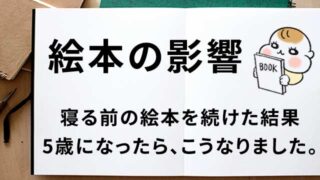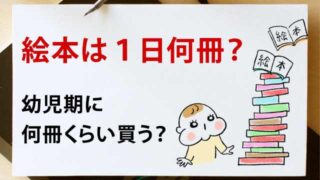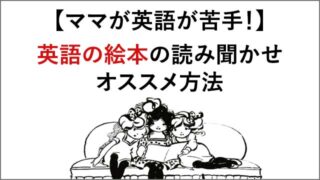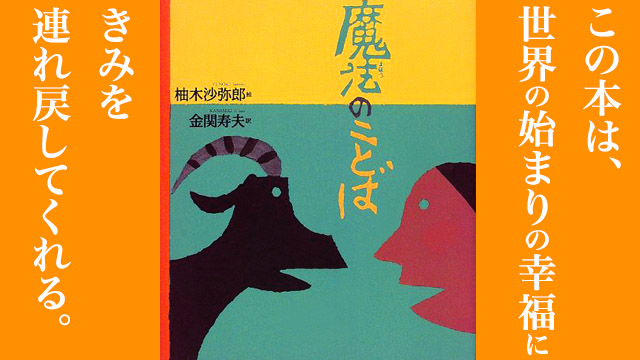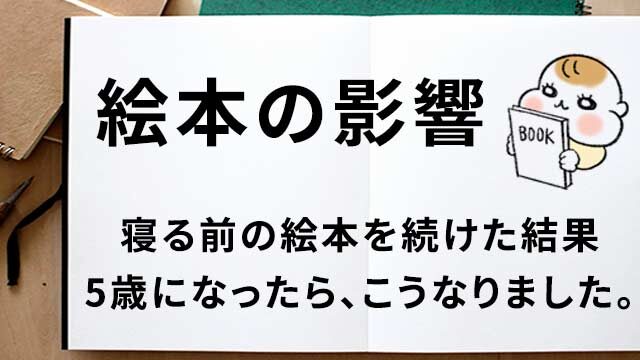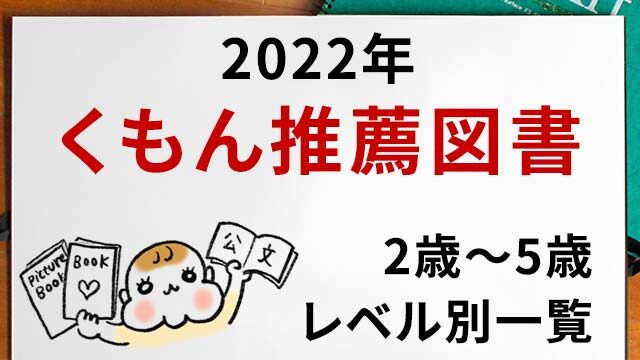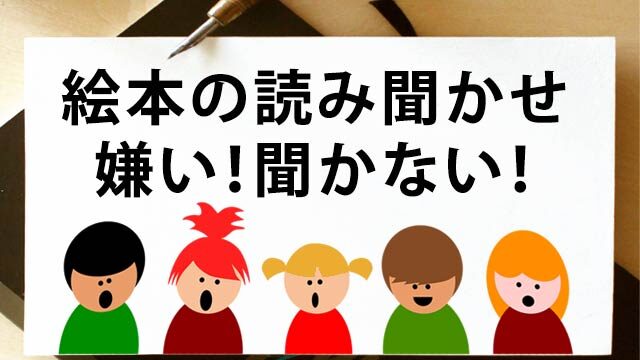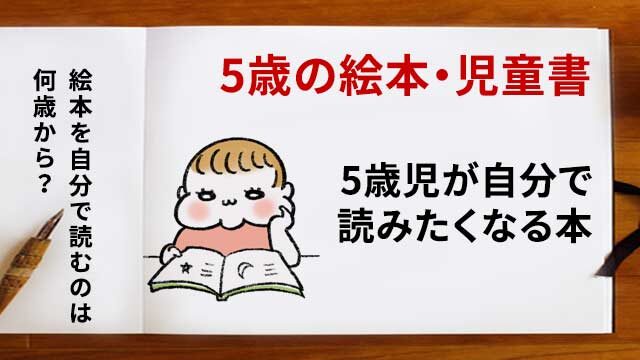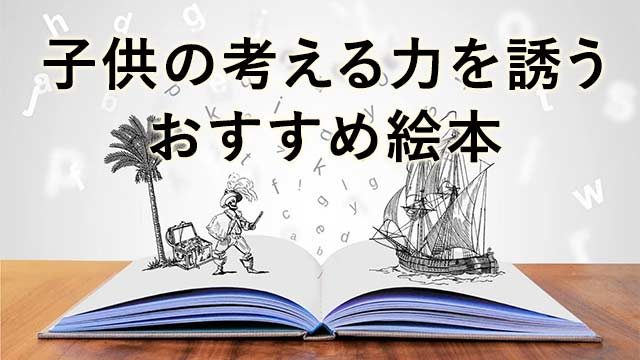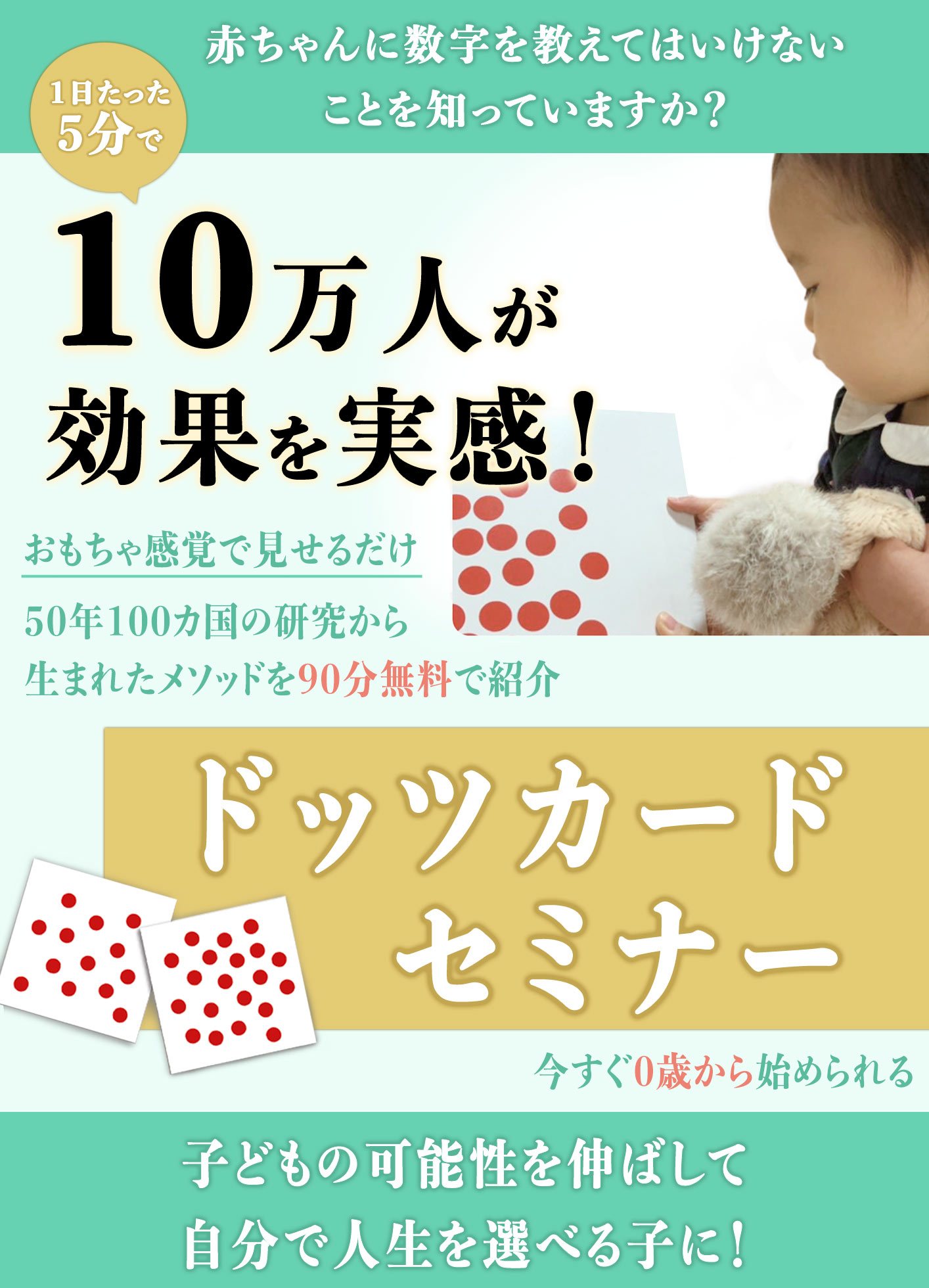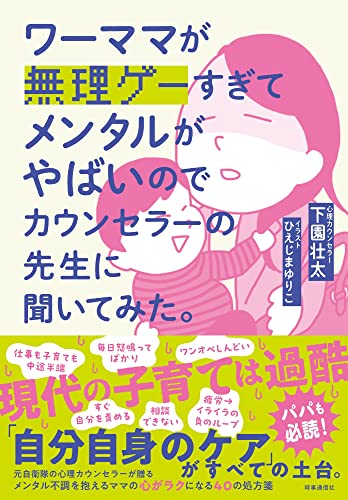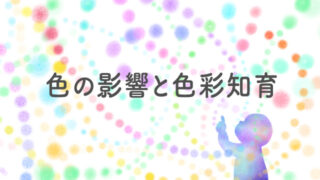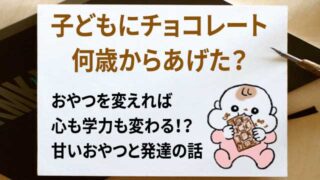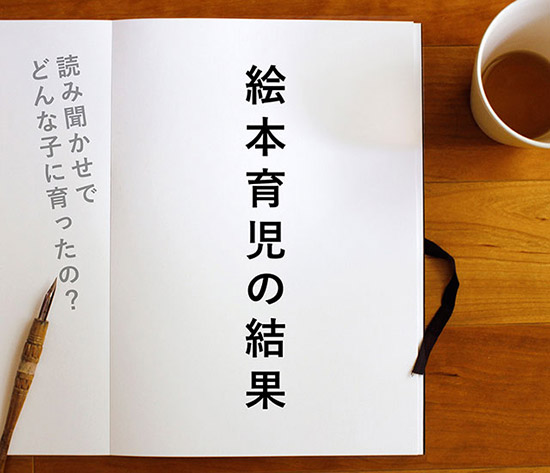
こんにちは、絵本大好きalpapaです。(@mamaschool)
幼児期に
絵本の読み聞かせで育った子たち、
絵本をたくさん読んだ子が、将来どうなったのか?
リアルな体験談レポートを聞いたのでご紹介します。
結論からいうと
「絵本が育てる子供の才能ってスゴイ!」です。
また、
「たくさん」って1日何冊読むの?
「絵本の効果とメリットは?」
という方は目次からどうぞ▼
目次
《絵本の効果》絵本の読み聞かせで育った子、小1になったらどうなった?
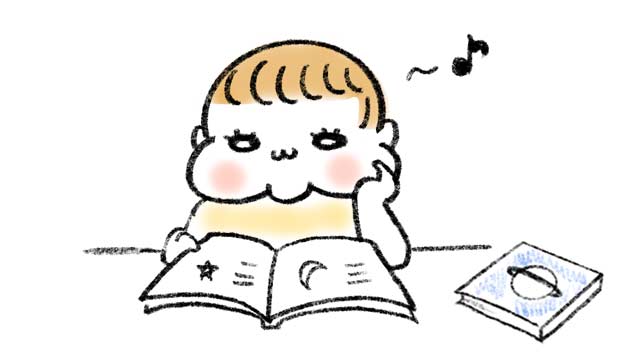
赤ちゃんからオススメされる
『絵本の読み聞かせ』
良いとは聞くけど、たくさん読んであげることで一体どんな子に成長するの?
【絵本育児の結果】を知らせるような話を聞いたので紹介します。
幼児期の読み聞かせが、小学生になる頃にはどんな効果を発揮したか、こうなりました▼
絵本をたくさん読んだ結果、こうなった
私の知り合いの製本作家さんで、
よく都内の小学校に製本のワークショップに行く作家さんがいるのですが、その方からこんな絵本話を聞きました。
とある小学校で製本ワークショップの日

その日は、みんなで製本したノートに俳句を作って書いてみよう!という課題。

担任の先生は「1つでもいいよ、ママと一緒にがんばろうね」
とはいうものの、なかなか難しい様子。
しかし、みんなが苦戦する中、

10個も20個もスラスラつ作っちゃう子がクラスに2人いたのです!!
スゴイ!
大人でもそんなにポンポン出てこない!
とすっかり関心し、保護者の方に話を聞くと・・・
「なんだろう?うちの子絵本が大好きで、
絵本だけは小さい頃からたくさん読んでるからかな」
「絵本のせいか、ひらがなの読み書きも自然と覚えたし」

「そういえばうちの子も絵本が好きで、
赤ちゃんの頃から読み聞かせしてました(*^^*)」
「特別な教育はしてませんが、
言葉も早かったですし、
絵本のおかげか考える力や想像力はありますね」
とのことでした。
なるほど、
絵本育児の効果、すごい・・・!
語彙が増えるだけでなく「想像力」や「感性」も磨かれる。
季節の情景や情緒をとりいれた“季語”を考えて、次々と俳句を作る、というのは語彙力があるだけではできないことです。
それよりもっと深い、
感性が豊かに育っていてこそ湧いてくるものです。
絵本というのは、
人としての深い部分まで育ててくれるのですね。
絵本は子供にとって
最強の世界拡大ツールと言われますが、内面的な世界も含め、まさにその通りだなと感じました。
知育に興味があっても
なかなか取り組めないママさんは、絵本だけでも毎日読んであげてください。
絵本をたくさん読んだ結果、こうなった②

追記で、
こちらは私個人の体験談です。
少し遅めの2歳から
寝る前の絵本の読み聞かせを始め、
5歳になったらこうなりました。
結果はこちら▼
【絵本の影響】絵本の読み聞かせを続けた結果、5歳になったら?
「読み聞かせ方にコツってあるの?」
という方へ、差がつく読み聞かせなら、こちらの本がおすすめ▼
絵本をたくさん読む事による効果

絵本の読み聞かせによる
効果やメリットをリストにするとこちら▼
・想像力が育つ
・語彙力、国語力が上がる
・集中力が上がる
・感性が豊かになる
・本好きな子になる
・親子のスキンシップになる
・子供の知識と体験が増える
・絵本は、子供にとって最強の世界拡大ツール
絵本をたくさん読む事で、
紹介したような想像力、語彙力、感性、とは別に、のちの国語力や文章読解力UPにもつながります。
また絵本は、
子供に知識と体験を与え、世界を広げます。
なぜかというと、
幼児期の子供は、まだ現実と空想のボーダーが曖昧なため、絵本で見聞きしたことを自分の体験のひとつとして錯覚します。
なので幼児は、
実際に体験したことがなくても
絵本で教えてあげれば「こう言えば相手は喜ぶんだな」「こんな事を言われたら悲しいんだな」と人の気持ちを学ぶことができます。
同じく、実際に見たことがなくても、
絵本で見聞きしたものは、現実の世界でも認識できるようになりるのです。
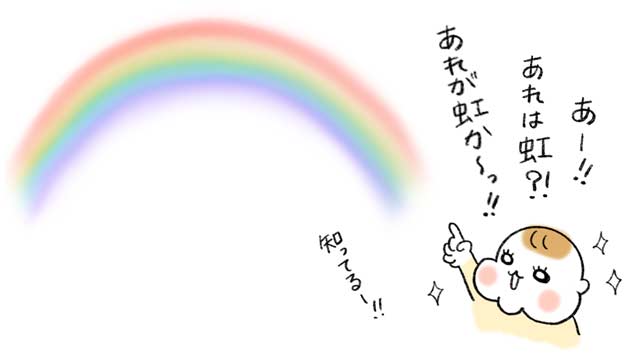
例えば、
絵本でしか「虹」を見た事がない子でも
現実で空に虹をみつけたら「あ、あれが虹か!」と認識できるのです。
絵本をたくさん読む事によって、
子供の知識も体験も増えます。
絵本はまさに子供の世界拡大ツール。
こども世界が広がるので、たくさん読んであげてくださいね^^
寝る前の時間に読むと、
より記憶と心に定着しやすくオススメです。
絵本をたくさん読むとは、1日何冊くらい?
『1日最低1冊絵本育児』とは言われますが、理想とされる目安は
1日10冊です。
これは幼児塾などで推奨される冊数で、
「絵本は1日何冊読めばいいですか?」
とプロに聞くと、たいてい
「無理なく楽しめる範囲でOKですが、可能なら1日10冊読んであげてください」と言われます。
といっても、
1日10冊は読まなきゃ!
と義務にならないよう注意です。
何冊読むかにこだわるより、
1冊だけしか読めなくても、
親子で楽しむ方を優先してください。
何歳までが1日10冊?
実際に絵本の効果が出た結果、何歳まで何冊くらいがよかったか、読み聞かせの頻度などの体験談はこちら▼
【絵本は何冊?】絵本の読み聞かせは1日何冊くらい読めば効果がでるか
【読み聞かせ】同じ絵本を繰り返し読む効果
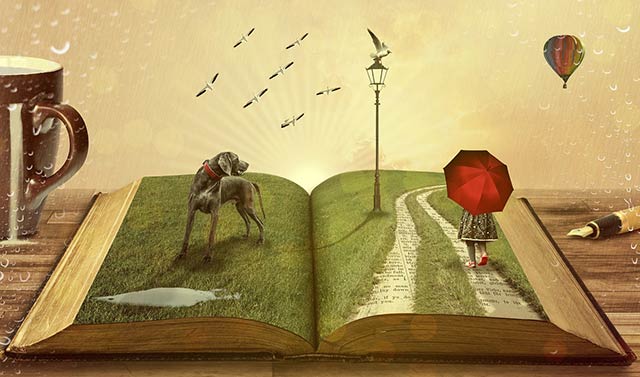
同じ絵本を何度も読まされる「おかわり絵本」一度お気に入りを見つけるとそれしか読まないくらい何度も読みたがりますが、これはとても良いことです。
何度も繰り返し読んであげて、
子供が暗唱できるほど読みまくってあげてください。
暗唱の効果はすさまじく、
たとえ意味がわからず声に出していたとしても自分の声で聞いた言葉はすぐに自分のものになります。
語彙が増えるだけでなく、
言葉がイメージとなり、文章の表現も暗唱しているうちに自分のものになっていきます。
そしてこれは将来的に
思考力、ライティング能力、読解力などに生きてきます。
例えば、
昔は本を読むといえば
「声に出して読む」という教育が一般的でした。
江戸時代、日本人の識字率は世界一だったと言われますが、その背景には江戸時代の『寺子屋教育』があります。
子供たちに寺子屋で古文や漢文をひたすら暗唱させるという教育法です。
声にだして何度も繰り返し読んでいるうちに、いつの間にかその文の中の「言葉、意味、表現、感性」にいたるまで、まるごと自分の一部にしてしいくのです。
子どもに読み聞かせたい
オススメの絵本はこちら▼
・考える力を伸ばす絵本
考える力を育てる絵本『思考・想像・疑問』を誘うオススメ絵本
・美しい絵本集
美しい絵本・絵が綺麗な絵本【子供に読み聞かせたいオススメ絵本】
・くもん推薦図書
【2022年・くもん推薦図書】2歳〜5歳のレベル・年齢別一覧!
英語絵本の読み聞かせ、やり方やオススメは?
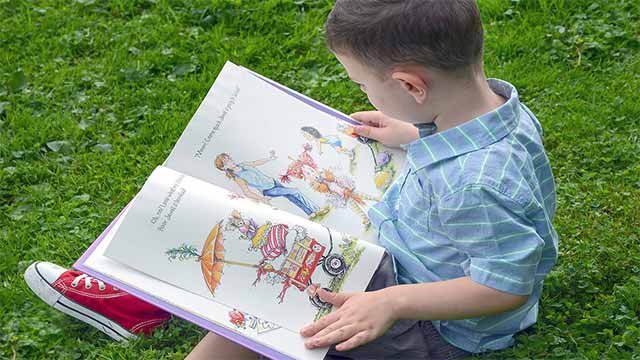
英語でも絵本を読み聞かせたいけど、
ママが英語の発音が苦手…
どんな絵本がいいかわからない、という方は絵本+絵本の歌CDがオススメです。
知育ママに人気で、
よく選ばれている英語絵本(+歌CD)のショップこちら▼
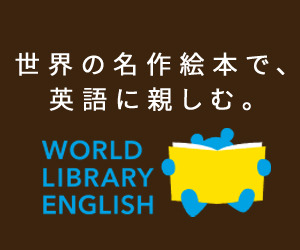
↑英米の名作絵本を翻訳出版している出版社で、Audio CD付きの英語絵本を出版しています。
この絵本が人気な理由は、
付属のCDに以下の3つが収録されていること。
❶ネイティブスピーカーによる朗読
❷ネイティブが英語を話すリズムごとに区切った音源
❸ストーリーを英語で歌った音源
特に「歌」で絵本の文章を暗記する子が多く、ママが英語を話せなくても、子供が楽しんで英語絵本を読むと好評です。
ただし、1歳3ヶ月〜推奨
1歳以下は直接のふれあいの中でこそ効果のある時期。
スキンシップや生声で”直接体に触れられながら聞いた言葉”に対して脳が大きく活動することがわかっており、赤ちゃんにCD学習は効果的ではありません。(詳しくはこちら)
またこちらの翻訳出版社は、
月1300円で年齢に合わせた翻訳絵本の定期便サービスも行っているので、図書館が近くにない方や、定価より安く、プロが厳選した絵本がいいという方にはおすすめです▼
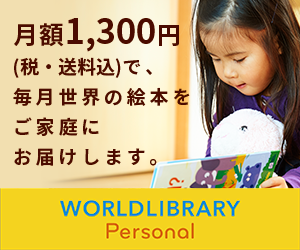
また、読み聞かせ方法として
英語が苦手な方におすすめはこちら▼
【読み聞かせの効果】絵本をたくさん読んだ子が小1になった結果は?
それでは、
いろんな絵本を楽しんでください。
『絵本育児』は知育にも将来的にも良いことづくしですよ(*^^*)